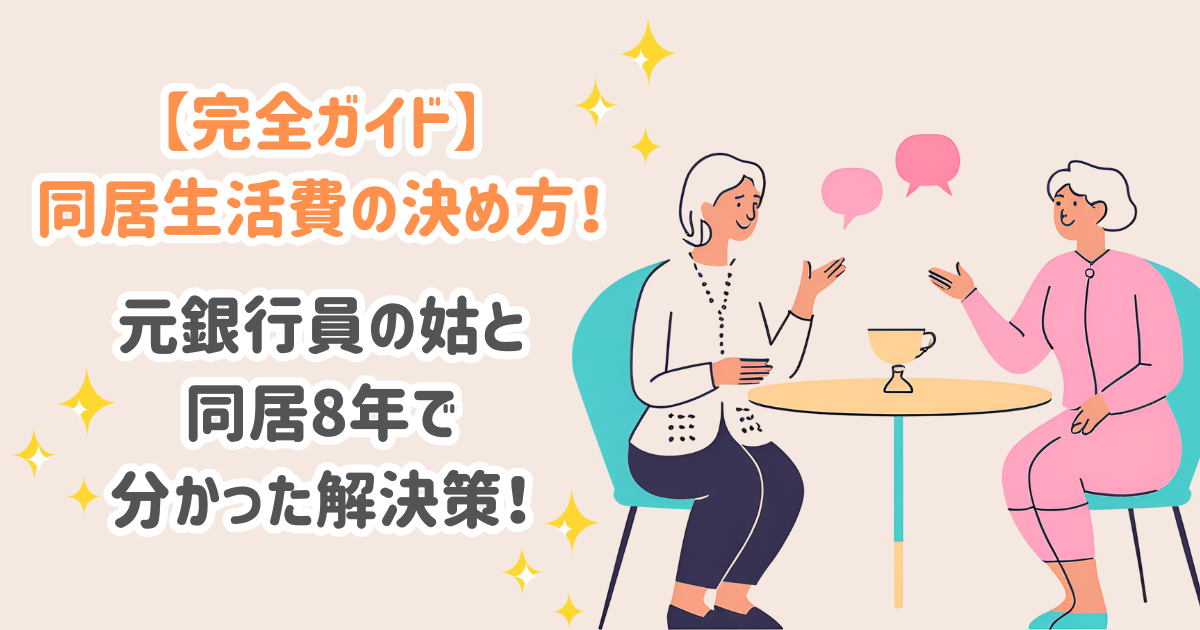こんにちは!元銀行員の義母と8年間同居していた2児の母、しおりです。
中学2年生と小学2年生の息子を育てながら、「同居の生活費の決め方」に悩んできた私の経験をお話しします。
私は月収15万円のパート、夫は手取り25万円の会社員という、ごく普通のサラリーマン家庭です。
一方、義母は元銀行員で、現在はパート収入と年金、遺族年金があり、家計に対する考え方も私たちとは大きく異なります。
今回は、そんな価値観の違う義母との同居生活で見つけた、生活費の決め方についてご紹介します。
同居生活費を決める前に知っておくべきこと
義母の収入状況を把握する
同居を始める前、義母の収入状況を把握するのに苦労しました。
「お金の話は気にしなくていいのよ」と、具体的な金額を教えてくれなかったんです。
銀行員時代は年収800万円以上あった義母は、お金に対してとてもおおらか。
「細かいことは気にしない」が口癖でした。
そんな義母に、現在の収入状況を話してもらうまでに3ヶ月かかりました。
仲介してくれたのは夫です。
「母さんの老後のためにも、きちんと家計を把握しておきたい」という夫の説得で、ようやく収支を共有してもらえました。
結果、義母の収入は以下のような状況と判明:
- 年金:月15万円
- パート収入:月8万円
- 遺族年金:月10万円
これを知って、私たちの生活費分担の考え方も大きく変わりました。
【アドバイス】
同居前に必ず確認すべき項目:
- 各種年金の受給額
- 就労収入の有無と金額
- 預貯金の概算
- ローンなどの支払い有無
- 生命保険の支払い状況
生活スタイルの違いを知る
義母は現役時代、家計簿をつけたことがないほどのどんぶり勘定でした。
「好きなものを好きな時に買う」がモットーの人です。
一方、私はパート収入の中でやりくりする生活に慣れています。
この生活スタイルの違いは、特に食費の使い方で顕著でした。
- 義母:「おいしそうだから」と即決で高級食材を購入
- 私:特売品を探して、まとめ買いが基本
【実体験】
同居1ヶ月目、義母が購入した高級和牛(1万円相当)を見て、私は内心パニックに。
でも、息子たちが「おばあちゃんのお肉、美味しい!」と喜ぶ顔を見て、「たまにはいいかな」と思えるように。
ここで学んだのは、「相手の価値観を否定しない」という大切な教訓でした。
キッチンの使用ルールを決める
これは本当に重要なポイントです。
朝は息子たちの部活弁当と朝食の準備で、キッチンが大混雑になっていました。
【失敗談】
同居開始直後は、キッチンでの作業時間が重なり、毎朝がストレスの連続でした。
- 私:朝6時から息子の弁当作り
- 義母:同じ時間に朝食の準備
- 結果:シンクや調理スペースの取り合いに
この経験から、以下のようなルールを確立:
- 時間帯による分担
- 夜(21時以降):私の作り置き時間
- 朝(6-7時):私の弁当作り
- 朝(7-8時):義母の朝食作り
- 調理器具の区分け
- 包丁・まな板:各自で保有
- フライパン・鍋:共用but使用後すぐ洗う
- 食器:共用と個人用を明確に分ける
- 冷蔵庫の使い方
- ドア:共用調味料
- 上段:義母専用
- 中段:私たち家族用
- 下段:共用食材
同居での生活費の決め方|2025年の我が家の場合
現在の生活費内訳
8年間の試行錯誤を経て、現在は月7万円を生活費として渡しています。
この金額は以下のように分配:
- 光熱費:3万円
- 食費:3万円
- 共用部分の消耗品:1万円
【金額の変遷】
同居開始時(2017年):5万円
- 光熱費:2万円
- 食費:2万円
- 消耗品:1万円
2020年:6万円に増額
- 光熱費:2.5万円
- 食費:2.5万円
- 消耗品:1万円
2024年:7万円に増額
- 理由:電気代高騰と食費の値上がり
この金額設定には、以下のような根拠があります:
- 光熱費の実態
- 電気代:月4-6万円(季節による変動あり)
- ガス代:月1-2万円
- 水道代:月1万円前後
→6人家族の実費を考慮して3万円と設定
- 食費の実態
- 息子2人の食費増加
- 食材の値上がり
- 共用部分の食材費
- 消耗品の内訳
- トイレットペーパー
- 洗剤類
- 掃除用品
- 電球など
【実体験】
この金額に落ち着くまでには、実に6回の改定がありました。
特に大きな転機となったのは、2024年の猛暑です。
中学生の息子の受験勉強で、エアコンの使用時間が大幅に増加。
電気代が月6万円を超え、これまでの生活費では全く足りない事態に。
その時の家族会議は、3時間に及びました。
結果として:
- 息子の勉強部屋の電気代は別計算
- 共用部分の光熱費を3万円に増額
- 使用量の記録をつける
という対策を講じました。
物価高時代の同居生活費の見直し方
定期的な見直しのコツ
【実体験】
以前は物価の変動があるたびに話し合いを持ちましたが、これが逆に関係をギクシャクさせる原因に。
現在は、3ヶ月に1回の定期見直しにしています。
具体的な見直し方法:
- 毎月の支出を記録
- エクセルで家計簿作成
- レシートは全て保管
- 公共料金の推移をグラフ化
- 3ヶ月分のデータを集計
- 費目ごとの平均額
- 特別支出の有無
- 季節要因の分析
- 家族会議での共有
- データの説明
- 問題点の指摘
- 改善案の提案
予備費の設定と運用
【具体例】
月々の生活費とは別に、「共同予備費」として2万円を積み立てています。
実際の使用例:
- エアコン修理(15万円)
- 予備費から10万円
- 残り5万円を折半
- 食洗機の買い替え(20万円)
- 予備費から15万円
- 残り5万円を人数割り
- 給湯器の修理(8万円)
- 予備費から全額支出
同居生活費トラブルへの対処法
コミュニケーションの工夫
【実体験】
最初の頃は、お金の話をすると必ず険悪な雰囲気になっていました。
特に、息子たちの食費増加について話し合った時は、義母が「孫のために使うお金を制限するの?」と感情的になってしまったことも。
これを解決するため、以下の方法を実践:
- 月1回の家族会議
- 日時を固定(毎月第一日曜の午後)
- 議題を事前に共有
- ポジティブな話題から始める
- デジタル化による情報共有
- 家計簿をクラウド化
- LINEグループで支出報告
- 写真でレシート共有
- 感謝の気持ちを言葉に
- 節約できた時は報告
- 美味しい食事への感謝
- 子どもたちからの感謝も大切に
支払い方法の工夫
現在実践している方法:
- 固定費
- 口座引き落とし
- 引落日を統一
- 通帳を定期的に確認
- 変動費
- 現金で管理
- レシートは必ず保管
- 毎週末に精算
- 急な支出
- LINE Payで対応
- その日のうちに精算
- 記録は必ず残す
- 共同予備費
- 別口座で管理
- 使用時は全員で相談
- 定期的に積立
まとめ:2025年の同居生活費事情
物価高が続く今、同居の生活費の決め方には、より慎重な検討が必要です。
私たちの場合、8年間の試行錯誤を経て、ようやく全員が納得できる形に落ち着きました。
重要なポイントは以下の3点:
- 定期的な見直しの機会を設ける
- 3ヶ月ごとの確認
- データに基づく話し合い
- 柔軟な対応
- お互いの経済状況を理解する
- 収入の把握
- 支出パターンの理解
- 価値観の尊重
- コミュニケーションを大切にする
- 定期的な話し合い
- 感謝の気持ちを伝える
- 記録を共有
【プロフィール】
- 同居歴8年の主婦
- パート収入月15万円
- 中学2年生と小学2年生の息子の母
- 元銀行員の義母と同居中
- 家計のやりくりが得意
※この記事は私の実体験をもとに書いています。各家庭で状況は異なりますので、参考程度にしていただければと思います。